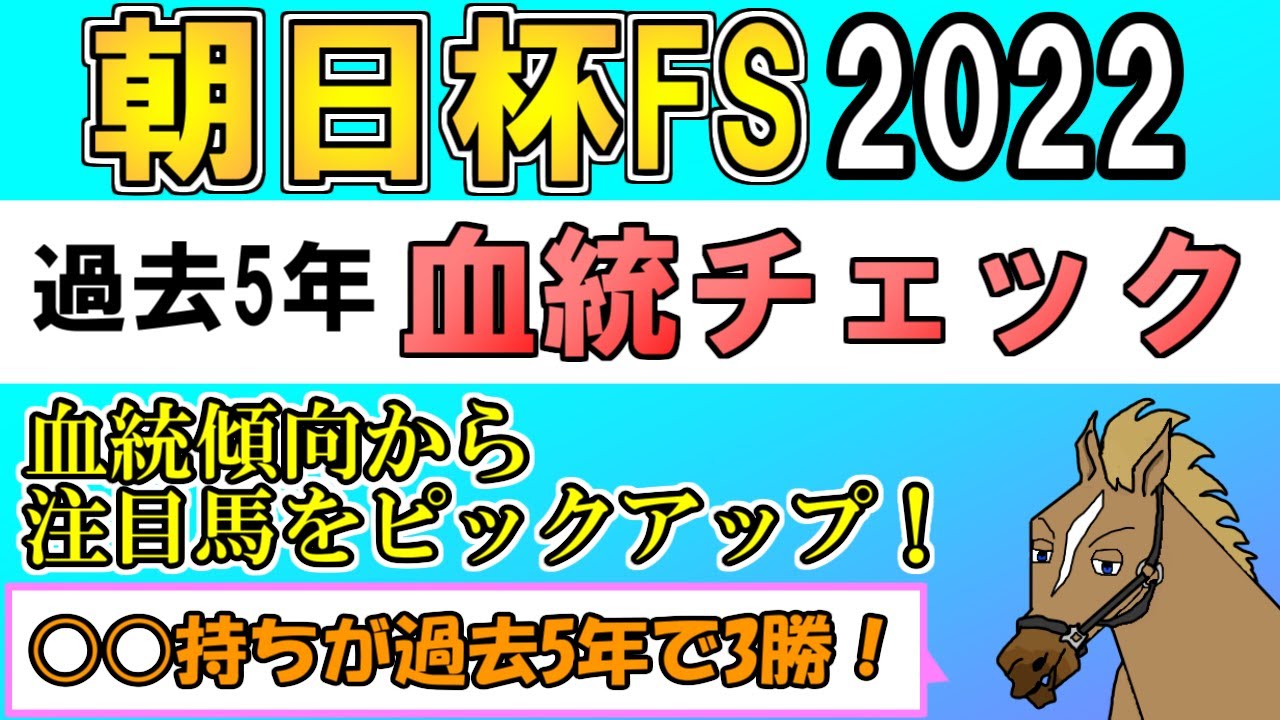フューチュリティステークスあるいはフュチュリティステークス(Futurity Stakes)とはオーストラリアのビクトリア州メルボルン近郊のコーフィールド競馬場にて秋に開催される競馬の競走である。
他のフューチュリティステークスと区別するため、開催国名を付して濠フューチュリティステークス、開催地の名を冠してコーフィールド・フューチュリティ、かつての主催者の略称を冠してVATCフューチュリティやVATCコーフィールド・フューチュリティ、現在の主催者のメルボルン競馬会(Melbourne Racing Club)の略称を冠してMRCフューチュリティステークスと称することもある。2014年時点では、興行上はスポンサー冠をつけてキャセイパシフィック・フューチュリティステークス(Cathay Pacific Futurity S)と公称されている。
1898年から行われており、概ね1400メートルで行われている。一般的な「フューチュリティステークス」が2歳戦であるのに対し、この競走は3歳上の競走馬に出走権がある。
概要
フューチュリティステークスは、1898年に創設され、創設以来、長い間7ハロン(約1408メートル)で行われてきた。1970年代にオーストラリアがヤード・ポンド法からメートル法へ移行すると1400メートルで行われるようになった。
オーストラリアで競走の格付けが始まると、1980年に最高格のグループ1(G1)に格付けされた。2006年からは「アジアマイルチャレンジ」シリーズの1戦となるため距離を1600メートル(約1マイル)に延長した。このシリーズは、オーストラリア、香港、日本、ドバイから1戦ずつが選ばれ、複数の競走で優勝したものには最高400万米ドル(当時の為替レートで約4億6000万)の賞金を与えるというもので、こうしたボーナス制度としては当時世界最高クラスの賞金を提供していた。しかし実際に賞金を獲得したのは2006年に1頭該当馬が出ただけで、2011年を最後に行われなくなった。フューチュリティステークスも2011年から距離を従前の1400メートルに戻した。また、この時期は経理代行業のパワーペイズ(Power Pays)社や美容関連企業のロックエボニー(Rokk Ebony)社がスポンサーになっていたが、年毎の賞金額の変動が大きく、70万豪ドルを提供した年もあれば、10万豪ドル程度の賞金だった年もある。
創設以来、1921年を除いて、戦時中も行われてきた。第二次世界大戦中はコーフィールド競馬場が軍事基地となったため、フレミントン競馬場で代替開催された。このほか1979年のみ1800メートルで行われ、1996年はコーフィールド競馬場の改装工事のためフレミントン競馬場で代替開催されている。
2014年現在は、メルボルンの秋開催「オータム・カーニバル」中に行われる。この開催の目玉競走は2歳馬による賞金100万豪ドルのブルーダイヤモンドステークスで、これに準ずるのがフューチュリティステークスとオークレープレートである。1400メートルの距離は、1200メートルぐらいを得意とするスプリンターと1600メートルぐらいを得意とするマイラーの両方を惹きつけるように意図されており、前者はしばしば馬齢重量戦のCFオーアステークスを経てフューチュリティステークスに挑んでくるものがいる。後者はフューチュリティステークスからオーストラリアンカップへ向かう事がある。
「フューチュリティステークス」とは
イギリスで発達した近代競馬では、かつては馬齢と共に馬が成長して一人前になると考えられており、7歳や8歳になってようやく本格的な競走に耐え得るものと考えられていた。やがて競走に使いはじめる年齢は徐々に下がっていき、18世紀の前半には「若馬」である4歳馬による競馬が始まった。3歳馬の競走が世間に認められるようになったのは18世紀の後半で、2歳戦は18世紀の末に普及した。しかしイギリスでは2歳馬の競走はあまり高い価値を与えられることはなかった。
1888年のアメリカのニューヨークで創設された「フューチュリティステークス」は、2歳戦でありながら全米最高額の賞金が提供され、大きな注目を集める競走となった。これを真似てアメリカ各地で同名の競走が創設されたので、いまでは大元の競走を発祥の地の名を冠して「ベルモントフューチュリティ」などと称する。
オーストラリアは19世紀のはじめ頃にイギリス人が競馬を持ち込んだが、大都市で本格化したのは19世紀半ばを過ぎてからである。メルボルン付近では1840年にフレミントン競馬場が作られ、1853年にはビクトリア競馬会(Victoria Racing Club、VRC)が組織され、大レースが行われるようになった。これに遅れて、1858年にアマチュア競馬の場としてコーフィールド競馬場が拓かれ、1898年からフューチュリティステークスが始まった。オーストラリアはもともとギャンブルに対する嗜好が強く、競馬はもっぱらギャンブルとして行われ、種牡馬はもっぱら本場イギリスからの輸入に依存していた。
コーフィールド競馬場は主にビクトリアアマチュア競馬会(Victoria Amateur Turf Club、VATC)が運営してきたが、2002年からはメルボルン競馬会が運営するようになった。
歴代優勝馬
- 「*」印は日本輸入馬を示す。
脚注
参考文献
- 『世界の競馬場2オーストラリア/ニュージーランド/香港/マカオ』ハイランド真理子著、中央競馬ピーアール・センター刊、1994
- 『競馬の世界史』ロジャー・ロングリグ・著、原田俊治・訳、日本中央競馬会弘済会・刊、1976
- 『サラブレッド』ピーター・ウィレット著、日本中央競馬会・刊、1978
- 『海外競馬完全読本』海外競馬編集部・編、東邦出版・刊、2006、ISBN 978-4809405242
- 『サラブレッド種牡馬銘鑑』第2巻、日本中央競馬会・刊、1972
- 『サラブレッド種牡馬銘鑑』第10巻、日本中央競馬会・刊、1989
- 『日本の種牡馬録3』白井透・著、サラブレッド血統センター・刊、1977
- 『Register of Throughbred Stallions of New Zealand Vol.IX』,The New Zealand Throughbred Breeder's Association(Inc),New Zealand Blood-Horse Ltd.,1976
- 『Register of Throughbred Stallions of New Zealand Vol.XI』,The New Zealand Throughbred Breeder's Association(Inc),1980
- Horse Racing Info Futurity Stakes
注釈
出典